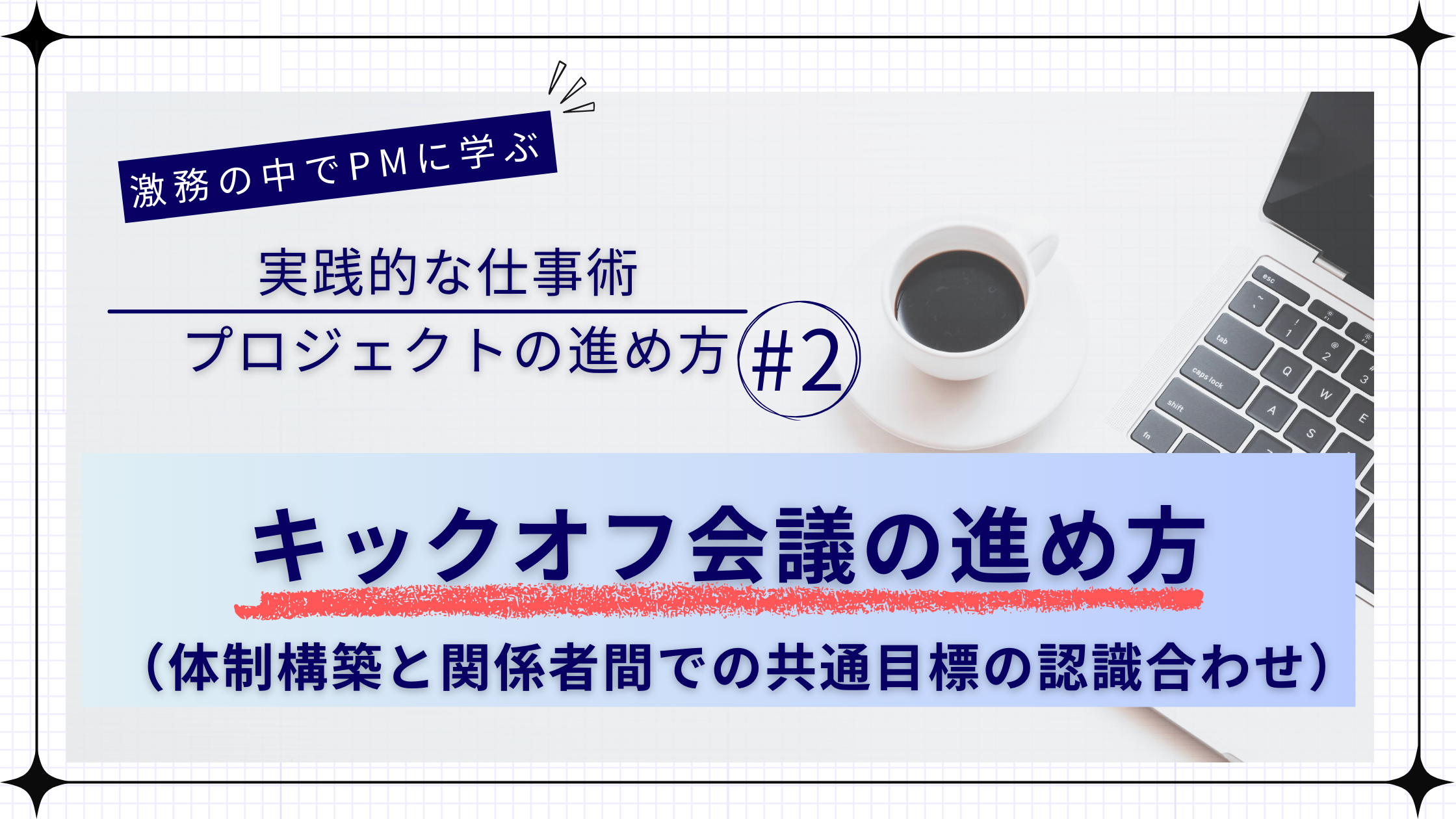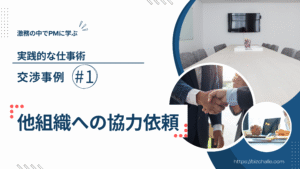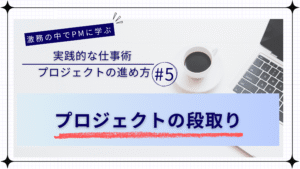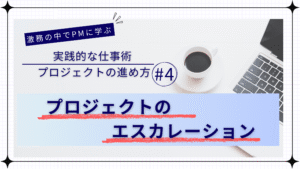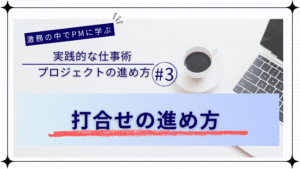これまでの投稿(流れ)
前回、プロジェクトを開始する最初のステップとして下記を投稿した。今回は、この続きとなる。
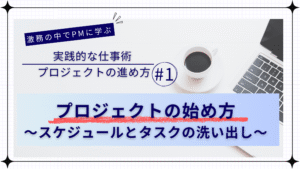
これを実施する目的/なぜこれが重要か
前回の投稿<リンク設定する>でプロジェクトを推進するために協力が必要な関係組織を洗い出した。
キックオフミーティングとは、この関係組織を集めてミーティングを行い、メンバー全員でプロジェクトの明確な目指す姿(ゴール)と完了日、各メンバーの大まかな役割分担を認識合わせし、ゴールに向かって取組む体制を構築することを目的とする会議である。
プロジェクトは自部署だけではできないものが多いため、この体制構築、役割分担、意識形成が欠けていると、思うように関係組織に動いてもらえず(又は動かすことができず)支障が生じるため重要なステップとなる。
この記事では下記の内容を整理していく。
- キックオフミーティングでの議題
- 会議参加とメンバーアサインの依頼と事前の協力の取付け(根回し)
- プロジェクトの概要・課題・スケジュールの共有
- 役割分担の意識合わせ
- 現時点で思いつく課題のディスカッション
キックオフミーティングでの議題
キックオフミーティングは、前述の目的を達成するため下記の議題で進める。
- プロジェクトの概要・目指す姿・体制
- スケジュールとプロジェクトを推進する役割分担案
- 現時点で思いつく課題のディスカッション
最後に、次回の打合せ日程とそれまでに実施する宿題の整理を行う
会議参加とメンバーアサインの依頼と事前の協力の取付け(根回し)
関係組織へキックオフミーティングへの参加依頼を事前に打診し、概ねの協力の取付けておく。
ただし、この時点では協力に後ろ向きな組織もありうるため、その場合は、キックオフミーティングで説明したうえで協力を取付けることとし、この時点ではキックオフミーティへの出席を最優先に進める。
また、協力の取付け有無にかかわらず、依頼先組織内のプロジェクトメンバーのアサインも打診しておく。
キックオフミーティングへの参加依頼をするときに提供する情報は下記のものが必要である。
- プロジェクトの概要・現時点での課題
- 依頼先組織の協力が必要な理由(課題を解決するためにあなたの組織の力が必要など)
- スケジュール感(いつまでに完成させなければいけないか)
プロジェクトの概要・課題・スケジュールの共有
キックオフミーティングでは次のような資料構成(案)で説明を行うのがよいと考える。
(あくまで案なので、プロジェクト内容などに合わせて適宜変える)

- ■表紙
-
- ここで重要なのは、打合せの議題を示すこと。
- 議題を示すことで、参加者に、何を決めていく打合せなのかをインプットでき、目的意識を持って打合せに参加してもらうことが出来るためだ。

- ■プロジェクト概要
-
- このページでプロジェクトの全体像を参加者に認識してもらう
- 特に大事なのがプロジェクトが目指す姿(ゴール)を認識してもらうこと!
- 目指す姿が合っていないと意識にズレから打合せなどがかみ合わなくなってくるためだ。
- そして、ここで大まかな各組織の役割分担の合意を取る

- ■スケジュール
-
- スケジュールでは、全体のスケジュールと完了時期の認識合わせを行う。
- 特に、マイルストーンの時期が適切かどうか、関係組織に確認を取る。
- 各組織に実施してもらいたいスケジュール感は持っていても空けておく!その理由は下記の通り。
タスクのスケジュールは担当組織が責任をもって実行してもらうために担当組織に出してもらう。自分たちが作ったスケジュールを自ら遅らすという無責任なことは人の心情としてしにくくなるためだ!
役割分担の意識合わせ
体制図・スケジュールを見ながら、各組織に実施してもらいたい役割を伝え合意を得る。
役割分担の協力を得られない場合は、妥協点を探す協議を行う。その場合は次のポイントに注意して協議を行う。
役割分担の協力を得るためのポイント
- 協力してもらわないとプロジェクトが進まない論理的な理由を説明する
■例えば
本プロジェクトが成功すれば将来の継続的な会社売上に貢献する。だからプロジェクトの成功が必要だが、○○の部分は△△部にしか実施できるスキルがない。 - 「相手が出来る範囲はどこまでか」、「どの様な協力ならできるか」を確認する
- 協力するために課題がある場合は、その課題解決を一緒に行う姿勢を伝える
■例えば
人員が不足している課題があり協力に難色を示している場合は、人員確保のための幹部エスカレに一緒に参加し説明するなど)
現時点で思いつく課題のディスカッション
ここまでで、プロジェクト概要、現時点の課題、スケジュール感を共有できたため、参加している関係組織から、その他の課題がないかや、課題の解決方法などのディスカッションを実施し、次回以降の具体的な課題解決打合せに反映する。
各組織はプロジェクト概要を初めて聞いた段階のため、この段階ではあくまでプロジェクト概要から考えられる課題のディスカッションとし、具体的な課題の解決方法に向けたディスカッションは次回以降の打合せで実施する。
■例えば
- 情報セキュリティの課題
-
- プロジェクトで得る情報にはお客様にとってセキュリティの高い情報が含まれるため、登録するシステムには情報を守るためのセキュリティ対策が必要、とか。
- 外注費を考慮したプロジェクト費用の管理が必要
-
- ○○作業は外注費が必要なため、外注費も考慮してプロジェクト費用の管理をする必要がある、とか。
次のステップ
次回は、個々の課題に対する具体的な実施事項(タスク)の洗い出しと、洗い出したタスクの役割分担、実施スケジュールの確認を行っていく。
そのため次回の打合せまでに、役割を負った各組織に「具体的なタスクとスケジュール」の提出を依頼する。
次の日程の調整を行ってキックオフミーティングは終了とする。
■この記事を書いて気付いたこと
自分が得意なことはすらすら段取りが思いつくが、プロジェクトの段取りはなぜか「段取りが分からない」と思ってしまう。
確かにやったことはないため何から手を付けていいか頭が真っ白になるし、苦手意識が生まれる。でも、やってることは段取りであって、特に難しいことをしているわけではないのではないか。
このブログでプロジェクトの段取りを復習していけば、知らない段取りではなく、知っている段取りに変わっていくため、もっと自信を持って苦手意識なく実行できるのではと感じた。
「特に難しいことをしてるわけじゃないんだ!」の気持ちでプロジェクトを進めていこう!!